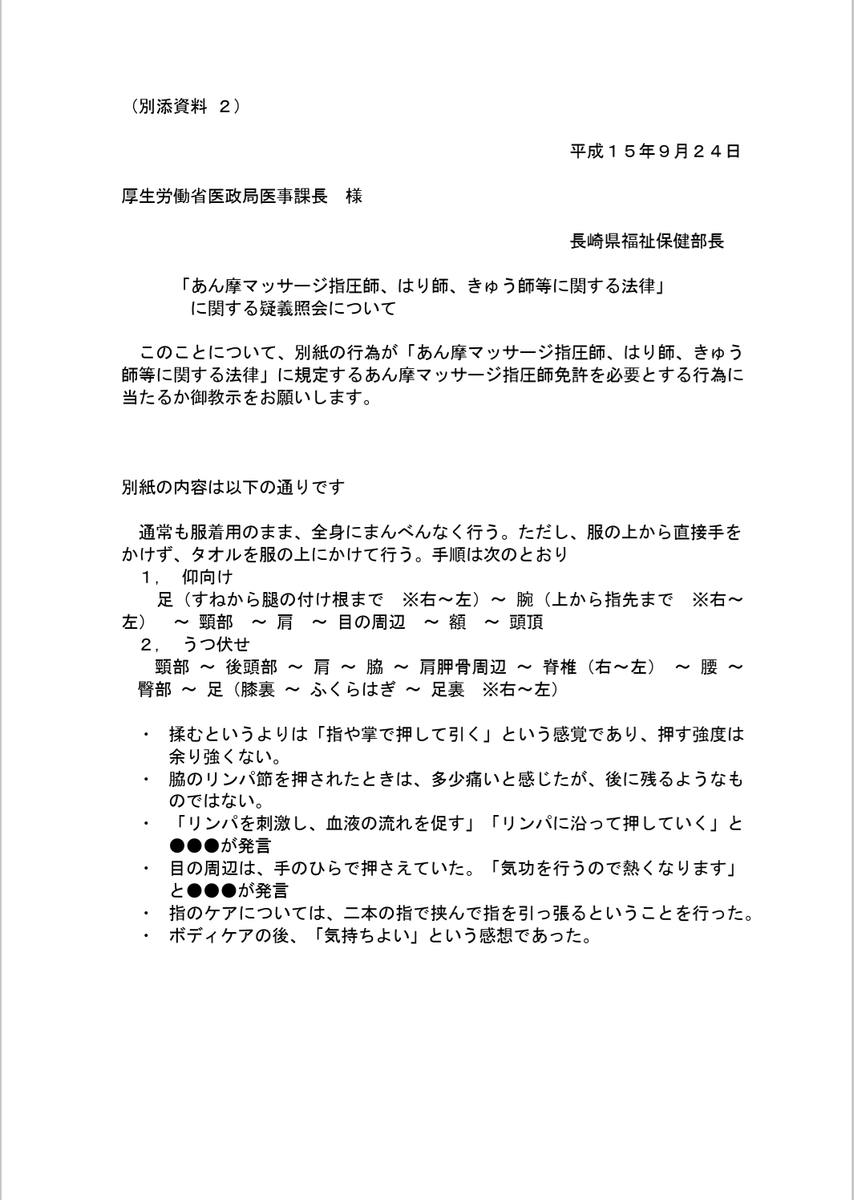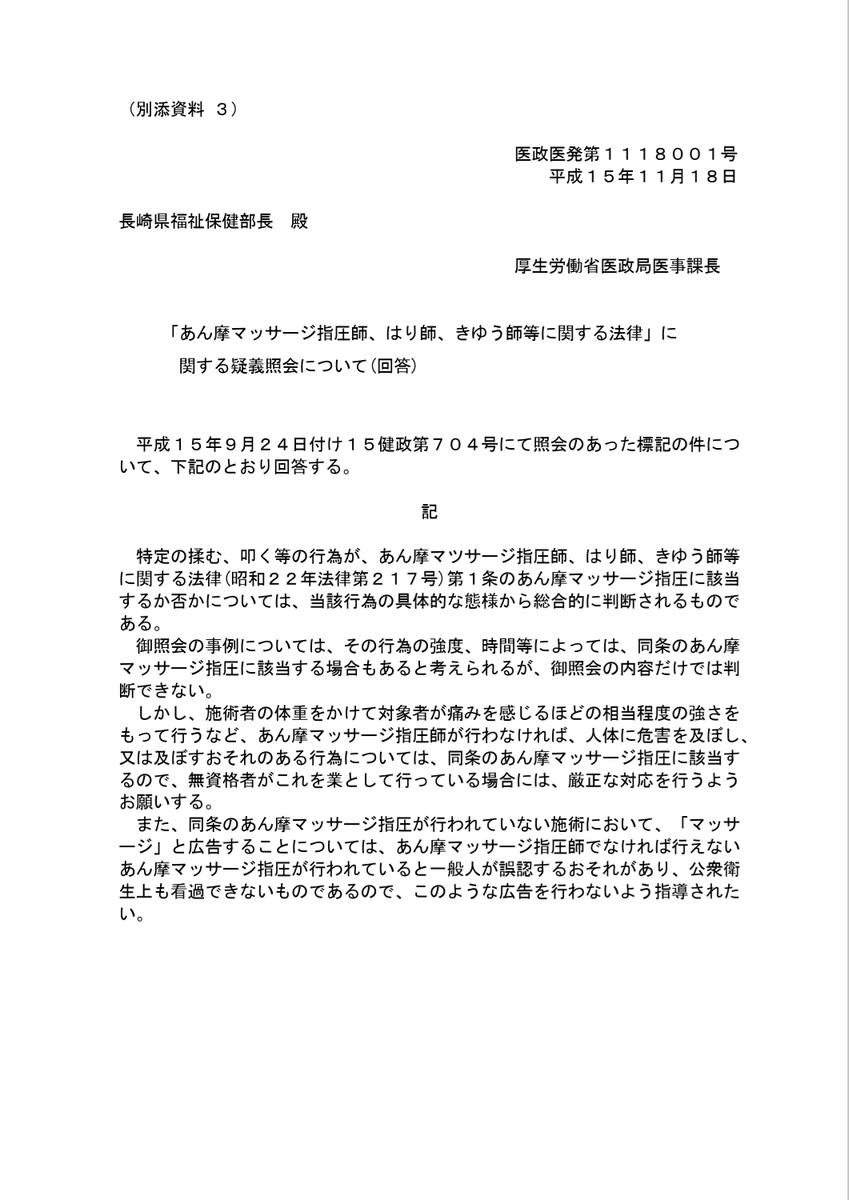一言:医行為の真似事をしたい既得権益側の目糞鼻糞
いわゆるリラクゼーション業界における争点の一つに「無資格者問題」がある。我が国においては医業類似行為としての「マッサージ」を業として行える者は「※あはき法」に規定される免許者に限定されるからだ。たとえば柔道整復師が行える医業類似行為は「骨折、挫傷、脱臼、打撲、捻挫」に限られる。また骨折と脱臼の施術をする場合は緊急の場合を除いて医師の同意が必要になる。しかし何れにせよ、あはき法の認めるマッサージであっても医業類似行為にすぎず、標準治療(通常医療)でない点を忘れてはいけない。
本邦において本来的意味としての治療、つまり医療行為たる標準治療(通常医療)を執り行う資格は医師のみが有するのだから。
平成16年11月04日
004/004 161
参 - 厚生労働委員会 - 2号
社会保障及び労働問題等に関する調査 無資格者対策
質問人
足立信也 民主党参議院議員
回答者
岩尾總一郎 厚生労働省医政局長
西博義 厚生労働副大臣
Q:次に、続きまして、あんま、マッサージ、指圧、医業類似行為についてです。
あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、カイロプラクティック、整体や足裏マッサージなどの医療の周辺産業です。
なぜ今回このような質問をするかといいますと、一つには医療の現場で、病院を受診する前にこういった業者に行き、麻痺や神経障害、骨折を起こす患者さんがいるということです。
もう一つは、私の地元の県議会の方から、医業に類似する行為について明確な基準がないので取り締まれないという要望があるからです。
まず、医業に類似する行為について、判例や厚生労働省の通知に基づいて私が解釈していることを述べます。
医業に類似する行為には、法で認められた医業類似行為と、法に規定されていない医業類似行為があって、法で認められた医業類似行為には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、略称があはき法です、に基づくあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうと、柔道整復師法に基づく柔道整復があります。
もう一つ次に、法に規定されない医業類似行為については、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務に限局して禁止処罰の対象になる、このように解釈しておるんですが、これでよろしいでしょうか。
A:よろしいかと思います。あはき法は、一条において、医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業とする者は、それぞれの免許を受けなきゃならないと規定しておりますし、柔道整復師法は十五条において、医師である場合を除き、柔整師でなければ、業としてその柔整を行っちゃならないということを規定しております。
それから、今のあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔整以外の医業類似行為についても、あはき法の十二条では禁止されておりますが、ここで禁止されているのは、先生おっしゃったように、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為に限られているということでございます。
Q:今の答弁で、あはき法の第十二条に、何人も、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう以外、医業類似行為を業としてはならないという条文があるけれども、最高裁の判決で、人の健康に害を及ぼすおそれがない場合は職業選択の自由があるのでよろしいということだと思います。
それでよろしいかどうか。あわせて、あはき法違反者、先ほどの法の違反者に対して実際にどのように規制を行っているか、その点について教えてください。
A:昭和三十五年の一月に最高裁の判決が出て、この十二条の禁止というのは、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為ということで限られました。

上掲した質疑にあるように、無資格者に禁止されるのは「法に規定される医業類似行為としてのマッサージ等」及び「法に規定されない医業類似行為」のうち「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」としての施術である。
「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。」と最高裁が述べているとおりだ。
考えてみれば当然だが、医師でもなく針師でもない者が、明らか侵襲を伴う針を人体へ打ってよいわけがない。
では純粋なリラクゼーション、つまり生体の変調を調整し疾病の治療や保健を目的とするものでなく、また下掲するような強圧を伴わない(通称)いわゆるマッサージは、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為なのだろうか。
そうではないと思う。
手技を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行う事業所をいう
最後に、医政医発第1118001号の疑義照会における厚生労働省の見解を確認しておこう。
弊ブログが紹介するタイ古式マッサージも(タイ本国においては伝統医学ではあるが)我が国においてはリラクゼーションの範疇であり、「人の健康に害を及ぼすおそれのない行為」としてのタイ民間療法(補完的健康アプローチ)を文化的側面からお伝えするものである。名称については文化的固有名詞「タイ古式マッサージ」の呼称を尊重し用いるものである。
>「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ人体に危害を及ぼす、又は及ぼすおそれのある行為については同条のあん摩マッサージ指圧に該当する。」
厚生省告示
仏歴2544年(2001年)
タイ方医事の一部として
タイ式マッサージ追加に関して
昨今、マッサージは広く普及し、症状軽減に関する科学の1つとみなされている。
しかし、いまだに法律上の規定がなく、実務において学術的規定に沿っている場合も、人々に危険な場合もあるなど、様々なことが起きている。
それ故に、2542年(1999年)発令の医療業務従事に関する法律の第5条(1)、第7条、第13条(2)に基づく権限により、厚生省担当大臣は医療業務従事委員会の推奨に基づいて、タイ方医事部への分類“タイ式マッサージ”の追加規定を、以下のように告示する。
項1)タイ式マッサージとは
診察、診断、症状軽減、病気予防、健康増進及びリハビリテーションを、押す、動かして押す、もむ、つかむ、ストレッチする、引っ張る、ハーブボールを当てる、ハーブサウナに入れる、又はマッサージ技術に従ったその他の方法で、或いは、薬事法に基づいたサムンプライの使用など、これら全てをタイ方医事の正規手順に基づいて行うことである。
(後略)
発行日 2544年(2001年)2月1日
コン・タッパラングスィー
厚生大臣
つまり次のように結論付けられる。リラクゼーション業の施術は【あはき師】でない事実のみを理由に「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為」つまり違法と認定されることはなく、専ら「個別の具体的業務様態から総合判断」されるにとどまるから、一義的には「人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為」と推定される。
追記〔2022.11.16〕
上本文を追認する重要な政府答弁を載せておきます。そして本文より正直めに書こう。答弁書
答弁書第六二号
内閣参質一九八第六二号
令和元年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
参議院議長 伊達忠一殿
参議院議員櫻井充君提出あはき法に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。
アーカイブ
https://archive.ph/pNqEZ
***
第198回国会(常会)
質問主意書
質問第六二号
あはき法に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和元年五月二十三日
櫻井充
参議院議長 伊達忠一殿
アーカイブ
https://archive.ph/U5gZN
私のコメント
しかし執拗ですね。自民党もひどいですが【メディカルジャパン立川】さんのHPもひどい。違法な施術例としてリラクゼーションを真っ先にあげてます。リラクゼーションを違法産業と断定してるようにしか読めない。メディカルジャパン立川HP
アーカイブ:https://archive.is/qYkJf
資格者はリラクゼーション事業所で発生する事故を殊更問題にするが、そもそもリラクゼーション事業所の提供する施術には実務経験のない下手くそな売れない国家資格者も含まれ施術事故は国家資格者の運営する事業所も含まれる。
そちら側も決して無事故なクリーン業界じゃないのだけれど、人の健康を害から守る教育を施せない国家資格の意義とは何だろう。
同資格制度は専ら視覚障害者保護を立法目的とする労働雇用にかかわる福祉政策だし(かつてGHQに指摘されたように)科学的根拠の乏しい東洋医学とりわけ中医学を医行為と認めるわけにもいかず効果も不確かである。
また当然に免許の有無は無事故安全健康を保障しない。
必然生じる矛盾を本来「医行為かそれ以外か」で考えるべきところ「医業類似行為」などという摩訶不思議な概念操作で誤魔化すから問題になるんだよ。
共存への一考
国家資格制度は維持しつつ現行の業務独占資格から名称独占資格に変更する。自分達の既得権益(業務独占)を守るために国民の健康を人質にとるの感心しない。聞こえのよい御為ごかしだろう。だって本当に国民の健康第一を考えてるなら科学的根拠の不確かな代替医療が(無資格者と差別化されうる)真正治療として提供される恐ろしい現実を是認しないはず。それほど医行為と医業類似行為の差は広い。途轍もなく。それが国家資格者の面子大事で治療のハードル下がるとかありえんでしょう。端的に医行為なめすぎ。
医業類似行為なんて中間領域は言葉遊びの中にしか存在できないのだから一律リラクゼーションとして扱い「あん摩マッサージ指圧師」を「公認あん摩マッサージ指圧師」に変更して名称独占させれば解決じゃないの。当然保険適用からも除外する。社会保障費負担を低減抑制する意味でも社会にメリットしかない。
付け加えると、介護業務の喀痰吸引等研修あたりも参考になる。喀痰吸引や経管栄養は医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」だが研修制度を設け現実の要請と上手く調和させてるでしょ。
そろそろ古い遺制を改革する時期なんだと思うよ。