過去へ言及する際、ほぼ必ず枕詞の如く…いやファイヤーウォールの如く張り巡らされる言葉の結界に、大抵の人はこれ以上先へと進めなくなる。だって一見もっともに聞こえるから。
しかし私はこう思う。
今は見えないけれど、誰にもわかっては貰えないけれど、時代の限界に埋もれざるえなかった「ナニか」が再び光を放ち、正しい名と適切な評価を与えられる未来がくる時を信じ散っていった者達だっているだろう。
未来へ託し託された者達の魂の胎動によって歴史評価が内部から修正されると何か問題あるんだろうか。
とはいえ、歴史自体と歴史評価とは弁別する必要があり、同一視してはいけないのは確か。実際、言語空間では両者の混同が多くみられる。
これは歴史記録の大原則。
このような形式を叙事文とよぶ。
従ってこの意味で「歴史を裁くな…」は間違ってはいない。
ただ、ルールを守ったうえで上述したような魂のバトンを受け継ぐのは自由だし、未来への教訓として特定の時代を再評価するのだって諸個人の自由。社会へ憚るような事ではない。
法の不遡及(Wikipedia)なんでこんな事をシコシコ書きなぐってるかというと、「かつて奴隷制が当たり前、当然の時代があった」などと宣う人がいたから。
刑罰法規不遡及の原則とは、実行時に適法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰すること、ないし、実行時よりも後に定めた法令によってより厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。
日本国憲法第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問はれない。
はっきり言います。
そんな時代はないです。
当然というための基準はもっぱら道理に因るが、これは衡平的正義を含む概念なので道理に照らさば奴隷制度は当然を満たさない。当然ではないが慣行的に容認されていた。少なくとも被支配者側視点では当然なわけないだろう。
このあたりが解釈として妥当じゃなかろうか。
当時は現代と異なり、「治者と被治者の自同性」原理が妨げられた悲惨な時代であった。そう評価してみせて、一体何が悪いのか。
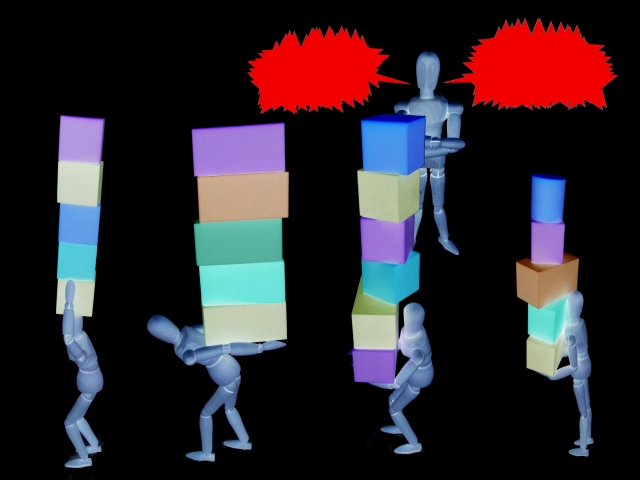
歴史を裁くな。
そう命じつつ、自分達は「支配者側の視点」のみを基準に据え客観視せず、単一の歴史的視座によって「当然」と断じているのだ。歴史を主観的に裁いているのはむしろ彼等側だろう。
ラダ・ビノード・パール