副題:我田引水の実例
最近の出来事なんですが、社会保険料の労使折半を【嘘】と喧伝する謎言説を肯定的に流布するイデオローグをSNSで見てしまって。端的にデマですが。
企業批判や会社の負担増正当化へインセンティブづけたいのか、なかには橘玲氏の著書から次の見解を引用してそう主張する人も。
あなたが毎月10万円の社会保険料を納めなくてはならないとすると、労使折半の原則に従って、半額の5万円は会社が支払ってくれます。これだけを取り上げて「社員になれば保険料の半分は会社持ちだから得だ」と考える人がいますが、これは大きな勘違いです。会社が支払う5万円は人件費の一部ですから、社会保険料の支払いがなければあなたがもらえるはずのお金だからです(社長がポケットマネーから出してくれるのではありません)。
『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方2015』(橘玲、幻冬舎、P162)』
何度読み返しても【保険料の支払いがなければあなたが貰えるハズのお金】理論を読み解けない。
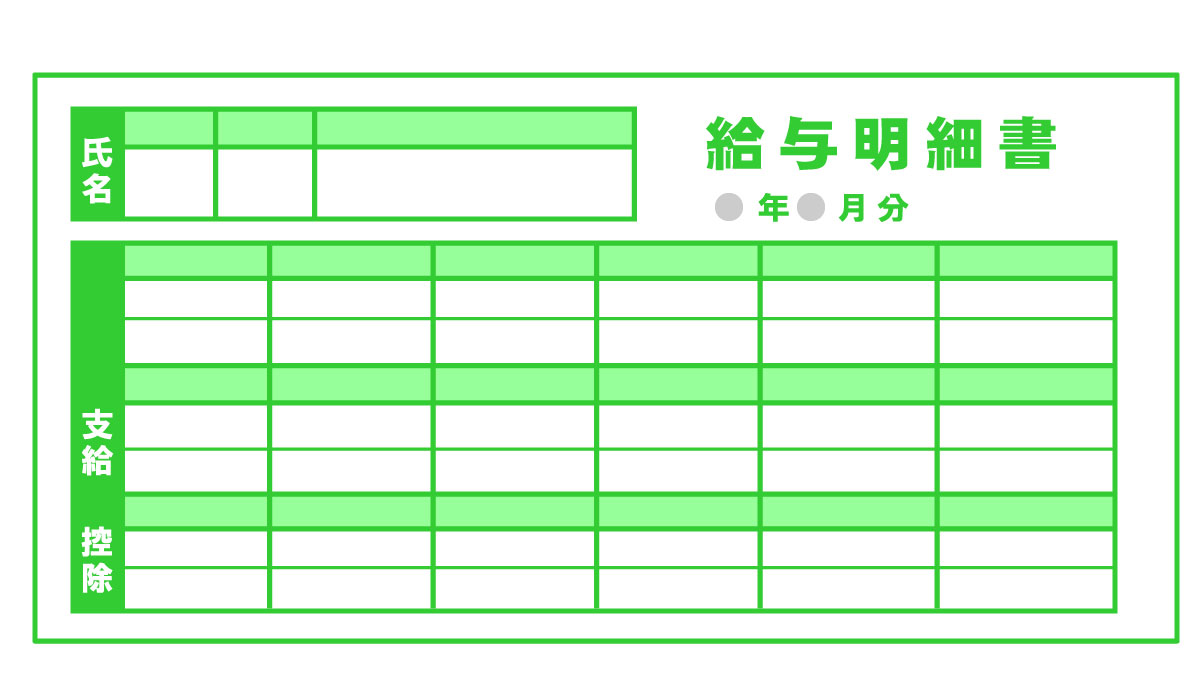
社会保険料(厚生年金)の計算式
【標準報酬月額×厚生年金保険料率÷2】に20万、20%(何れも仮の数字)をあてはめると従業員の差分は18万、【労使折半分÷2】がなければ16万だが社会保険制度が撤廃され双方納付義務から離脱した場合、自己負担分の2万のみならず会社負担分の2万も本来従業員の取り分だから月給は22万が適正値であり可処分所得へ充当される額はつまり当然に4万と言いたいわけか‥謎理論すぎる。
確かに社会保険制度なんてなくなれば会社は当該2万を負担する義務から解放されるわけだ。でも負担分2万の充当先が会社の金庫じゃなく何故に従業員のポケット?
文字通り我田引水。

我田引水[我 (ワ) が田に水を引く意]
強引に自分の都合のいいように計らうこと。
引用元:新明解国語辞典
事業主視点だと(労災保険のように性質上やむない負担もあると思うけど、)社会保険料は賃金のような労働対償性がないからを法律効果で折半義務を強制してるだけなのに、法律効果消滅を義務なき支払いからの解放と認識させず労働者への給与還元を当然視する誤理論が思った以上に広まって‥強引に自分の都合のいいように計らうこと。
引用元:新明解国語辞典
結論❌保険料の支払いがなければ
⇒あなたが貰えるはずのお金
⭕保険料労使折半がなければ
⇒会社が支出するはずのないお金
⇒あなたが貰えるはずのお金
⭕保険料労使折半がなければ
⇒会社が支出するはずのないお金